オープンファシリティセンターものづくりユニットの利用者に対して定期的に実施されている利用講習会*の内容について、同講習会に携わられているATECものづくり系 阪本 大夢さんにお話を伺いました。コロナ禍以降はオンラインでの実施も導入されていたことを含め、以前からお話をお伺いしてみたく思っておりました。
―― オンラインでの利用講習会の実施、いかがでしょうか(コロナ禍前は対面での実施だったのでしょうか)。動画や確認テストの作成について、苦労した点等ありましたら教えてください。
阪本 もともと利用講習会は対面で実施していました。パワーポイントを用いたユニット概要の説明ののち、職員が引率して実際にユニット内の機械を見学してもらうという流れで行っていました。
コロナ禍に伴い、対面での実施が難しくなったためオンライン化を進めました。


動画は対面で使用していた資料に読み上げ音声とテロップを載せたものを作成しましたが、動画編集には慣れていなかったのでかなり時間がかかりました。スライドショーを動画にしているのですが、音声とテロップのタイミングを合わせるのが予想以上に大変でした…
確認テストはオンライン実施になってから取り入れました。動画視聴だけだと見るだけで終わってしまうことと、Moodleの機能を使えば比較的簡単にテストを実施できることからテストを作成することにしました。
コロナ禍前はMoodleを使う機会がほとんどなく、作り出した頃は手探りで試行錯誤しながら作っていました。オンライン化して4年目ですが、毎年少しずつ改良しているため、だいぶ受けやすくなったのではないかと思います。
―― 動画もさることながら、危険予知資料、大変興味深く拝見しました!「研究意欲に溢れるサカモト君」を題材に問題点を記入していくこの資料、どのような効果を想定して作られたのでしょうか?
阪本 ありがとうございます!
危険予知資料は読むだけでどの機械がどう危険かができるだけ分かるように作りました。
どんな危険があるか自分で考えるきっかけとなればと思っています。
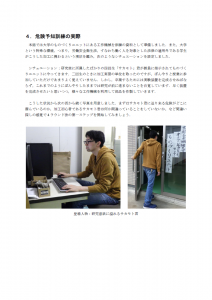


ものづくりユニットの所有している機械は使い方を間違えると大怪我につながるものも多く、機械によって注意すべき点も違います。対面で講習会を実施していた時からですが、講習会内で機械を実際に動かすことができないため、こういった資料で危険意識を高めてもらおうと考えています。
工作機械を扱ったことがない人には何が危険かわからないことも多いですが、パッと見たときに危険そうな部分をできるだけ多くしています。
また、工作機械を扱ったことがある人でも自分が作業しているときには気づきにくいこともあるため、客観的に作業の様子を見ることでより安全に作業できるようになると考えています。
―― 「使用頻度の多い機械や専門性の高い機械測定機*」の方は、やはり対面での実施なのでしょうか。こちらの講習会についても教えてください。
阪本 使用頻度の多い機械はボール盤や旋盤などの汎用機(自分でハンドルを回して操作する機械)ですが、これらはロボコンやフォーミュラの学生が使用することが多く、所属学生を集めて対面での講習会を定期的に開いています。

その他でユニットの機械を使用しに来る人については、個別指導のような形でその都度必要な時に講習を行っています。

専門性の高い機械測定機については、一応HPには講習会を行うと書いていますが、実際のところユニット職員以外が使用することはほとんどないため講習会を開いたことがなく、使用する場合は職員が傍について一緒に操作するという形をとっています。
―― 受講生の反応はいかがでしょうか。
阪本 アンケートなどは取ってないのであまり反応を聞く機会がないですが、やはりオンライン実施になったことで受講しやすいという声はありました。
他には、動画を見ただけですぐユニットの機械を使えるようになるわけではないので、実際に来てみないとわからないことも多いという意見もありました。
―― お忙しいところありがとうございました!使い方に加え安全面等、実にさまざまな視点から考慮・工夫された利用講習会、ということがよくわかりました。
*ものづくり系業務紹介ページの「1.1 講習会業務」より抜粋
年に2~4回程度、ものづくりユニットの利用講習会を開催しています。ものづくりユニット利用においては講習会の参加が必須であり、年間200名程の受講者が参加しています。また使用頻度の多い機械や専門性の高い機械測定機に関しては、機械毎の講習会も開催しています。